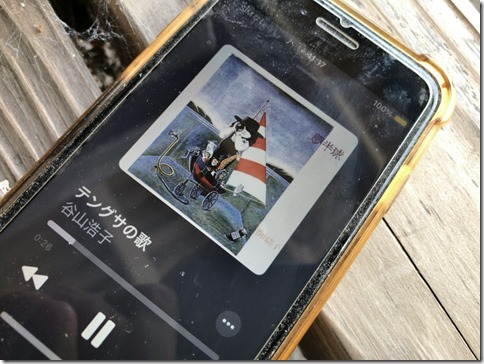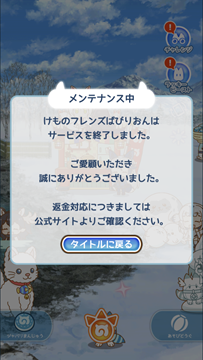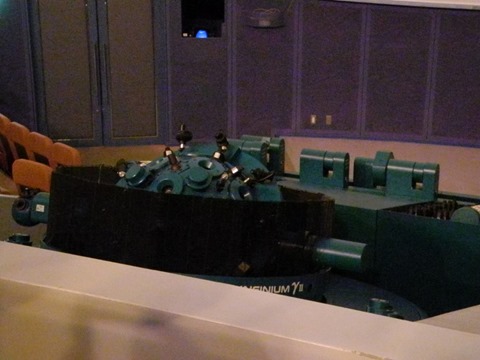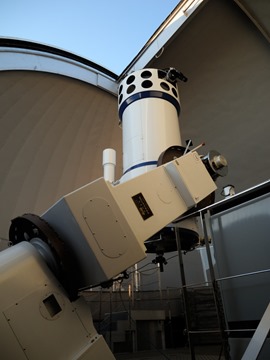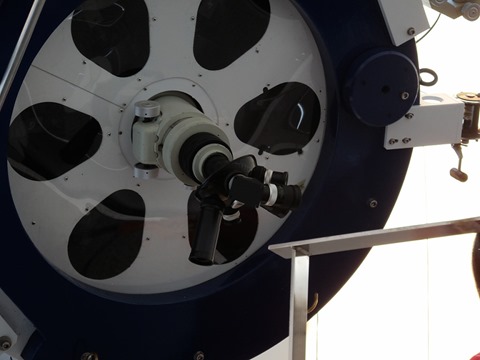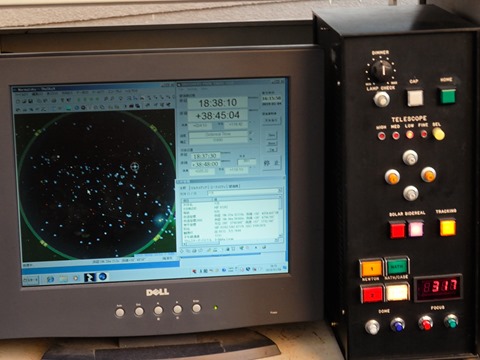人生に必要なもの、クロネコとキンモクセイ
涼元悠一
「クロネコとキンモクセイ」
そう答えた彼女の、得意そうな顔。
いつも空いてる喫茶店、いつもの窓際、二人席。
秋、そろそろ日が短くなってきた午後。生け垣に囲われた、昔の洋館を改装したらしい一軒家。お客はおあつらえ向きに、僕たち二人だけ。よく磨かれた木張りの床に、南向きの窓から日光がまだらに射している。
僕の質問はこうだった。
「人生に必要なものは?」
もっとちがう答えを期待していた。
でも、唇から転がりだしたふたつの言葉は、クロネコとキンモクセイ。
最初に会ったのはもう一年も前だ。
印象は、「見てると楽しい子だな」だった。
飾りっ気のない髪型とモノトーンな服装から想像したのと違って、中身はほわほわしてるというか、一風変わった感じだった。『電波系』とか『わざとっぽい』とか、露骨に嫌う奴もいた。僕が気にならなかったのは、初見ではそこまで入れ込まなかったからだ。
何度か会うと、見てるだけじゃ中身はわからないんだなと思った。
実用一点張りの真四角なポーチの中に、いつでも飴を入れている。でもそれがフランス製だかフィンランド製だかの不思議なデザインの包みで、ひとつもらってみると、まともに食べられないようなすごい味だった。吐き出しそうになったら、勿体ないから最後まで舐めて、と言われた。
「こういう味が好きなんだ」
「好きとかそういうのじゃないけど」
答えながら自分も一個口に放り込んで、まんざらでもなさそうな、幸せお裾分け的な顔をしていた。これじゃ褒め言葉に聞こえるか。でも、本当にそんな感じだった。
なんだかんだあって、付き合うことになった。
そこからまた色々あって、週末は僕の部屋で一緒に暮らすようになった。
機会を見て同僚だちに紹介すると、みんな口を揃えて「かわいい」「羨ましい」と言ってくれる。でもその何日か後、彼女の話題になった時、一通り褒めそやした後こんな風に付け加える。
「でも、いろいろ難しそうな子だよね」
僕には合わないだろうってことだ。わかっているし、これからも変わらないと思うし、変えたいとも、変わってほしいとも思わない。
つまり……自分で言うのも恥ずかしいけど、ベタ惚れしてる。一緒にいてしっくり来る。ケンカをしてもすぐに仲直りしたいと思える。だから一緒にいたい。できれば、できるだけ長く。
ついでにぶっちゃけると、あの時の僕は勢いでプロポーズ的なことを言い出すつもりだった。
日曜の昼間をいつも通りに一緒に過ごして、締めくくりに彼女お気に入りの喫茶店に入って、僕がブレンドコーヒーのホット、彼女が黒すぐりジャムのロシアンティーを注文した。一週間分貯まったとりとめのない話をたくさん聞いて、いい感じにくつろいだ雰囲気になって、向かいに座った彼女の横顔が、半分の月みたいに眩しく輝くのが妙に綺麗に映えて。
ずっとここに来れたらいいね、なんて話の流れになった。
こうなったらもう、行っとくしかないわけで。
「それじゃあさ、ひとつ質問なんだけど……」
僕は切り出した。
「人生に必要なものは?」
僕なりに考えて、僕なりに踏み込んで、気持ちを込めた言葉のつもりだった。
でも、彼女はまごつきもせず、ずばっと即答した。
クロネコとキンモクセイ。
もう一度言うけど、クロネコとキンモクセイ。
「なんで?」
「前にね、ものすごいお金持ちのヒトがいて」
いきなり雲行きが怪しい。そう思いつつ、僕は念のため確認する。
「仕事関係?」
「ううん、ぜんぜん別」
早く先が話したいんだろう、首をぶるぶる、即座に否定する。
「だって庭とか公園みたいに広いんだよ? 他にも家がたくさんあるって言ってたし。それでいろいろ興味津々で、でもどうしても聞いたことがあって」
「どんなこと?」
「『駄菓子屋買い占めとかもうしました?』」
三秒ぐらい、沈黙ができてしまったと思う。
「なるほど」
「なるほど、でしょ?」
「それで、お金持ちさんの答えは?」
「『は?』って言われた。失礼だよね。『は?』って」
「だね」
僕も二度ほど『は?』と言い返しそうになってるけど、それは置いておく。
「昔読んだ本にね、金貨をお店のおばさんに渡して、お菓子全部買い占める女の子が出てきたの。そういうのにもうずーっと憧れてて」
「買い占めて、全部食べるの?」
「ううん。好きなだけ食べて、食べきれない分はみんなに配るの。あと、おみやげにしてもいいし」
言いながら、無造作にカップを持ち上げて、鈴みたいに振るいつもの癖。
「あ。もうない」
「もう一杯頼む?」
「うん。次はウィンナティー飲まないとダメだから」
「こっちは別のでいいんだよね?」
「お好きにどうぞ-」
にっこりと笑って、その笑顔のままカウンターの方に「すみませーん」と呼びかける。
彼女がウィンナティー、僕は……結局ブレンドコーヒーホットのお代わり。オーダーを伝えるのもそこそこに、またこっちに向き直る。
「それでね」
幼少の頃からの夢であった『駄菓子屋買い占め』について、彼女は果敢に説明を試みたらしい。でも、当然理解してもらえるはずもなく。
「なんかね、いつの間にかワインの話になっちゃった。でも、全然美味しいとかじゃなくて。何ダース買っていくらだったとか、ずーっと持ってるどーにか言うワインが今は何十万円になってるとか。わたしにも一本くれるって言ったんだよ」
「ほんとに?」
「うん。だから言っちゃった」
「なんて?」
「ワインってやですよね。こぼすと落ちないし」
鼻白んだお金持ちの顔が見えるようだ。これだから電波系って言われちゃうんだろうな。あと、完全にとばっちりの高級ワインには同情する。
「素直にもらってきたらよかったのに」
ちなみに言うと、彼女はワインも大好きで、二人で一本空けることもある。僕がいなくても一本は簡単に空くと思う。
「だって、ワインの値段とか名前とか飲みたいんじゃないもん」
子どもみたいに口をとがらせたまま、言ってることは妙に鋭い。
「あー、やっぱりナントカタカイワインよりも駄菓子屋買い占めがいいなー」
「今度やってみる? さすがに買い占めはできないけど……」
「お金持ちじゃないから、禁止」
「禁止なんだ。それは厳しい」
「お金持ちキライだから」
空のカップをまた持ち上げてしまってから、すぐに戻してぶすっと言う。お金持ち大好きと言われるよりはマシだけど。
彼女にとっての幸せの中心は、いわゆる裕福ってやつじゃない。このまま二人でふわふわしたまま暮らしていけそうな気がするし、そうしたいけれど、できるものなんだろうか?
それを確認するために、「人生に必要なものは?」なんて言ったんだろうな。
つらつら考えていると、彼女がふうっと溜息をついたのが聞こえた。
「お金持ちって、いつもなにをしてるのかな? せっかくお金あるのに」
「そりゃまあ、ゴルフとか」
「ゴルフをしたかったからお金持ちになったのかな? お金持ちになったからゴルフをしたくなったのかな?」
「ニワトリが先かタマゴが先かだよね。それは」
「どっちが先?」
「いや、そう訊かれても……」
僕に答えられるわけがない。未だに正解が得られていない、人類永遠の難問だ。
「要するに、お金持ちになることは人生において必要じゃない、と」
「うんそれ、だいたいそんな感じ」
僕は無難にまとめ、彼女は鷹揚にうなずく。
「だから、クロネコとキンモクセイ」
そしてようやく、会話は元の場所に戻ってきた、んだろうか?
「お金持ちになっても、温室とかでキンモクセイ育ててっていうのは違うから」
「うん。だろうね」
「今日みたいな日にね、よく晴れてて、ぶらぶら散歩してて、ちょっと寒くなってきたなって感じで、あれ? って思ってくんくん匂いかいだらそこにあるのがキンモクセイ」
木そのものだけじゃなくて、周りのシチュエーションもひっくるめてのキンモクセイってことだろう。きっと。
「キンモクセイ好きだったんだ」
「ううん、そんなに」
ぷるぷると首を振る。僕は困ってしまう。人生に必要なものは? そう訊いたはずなんだけどなあ。
「あ、ちがうちがう。キンモクセイだけじゃダメってこと」
「じゃあ、やっぱりクロネコも?」
「うん、クロネコも。でも、それだけじゃダメ。仔猫の時にある日突然迷い込んで来ないと」
また条件が厳しくなった。
「色が黒ってとこも譲れない?」
「うん。ゆずれない」
「そりゃまたなぜ?」
「なぜでも」
「そこを何とか説明をお願いしたい」
「うーん、敢えて言うならー」
しばし考えてる顔を見せ、それからあっけらかんと答える。
「クロネコって、それだけだとネコって感じがしないから」
「うーん、そんなもん? 個人的には猫オブ猫って感じがするけど、黒猫」
「うんうん、そんなもん。あんまりネコネコしてるのは好きじゃないんだ、きっと」
……まあ、そこは今拘るべきところじゃない。話を戻そう。
「僭越ながら、ここまでの流れをまとめさせてもらうと」
「まとめてみて」
「最初からそこにあったみたいなキンモクセイと、それにぴったりなクロネコがセットで必要であると」
「うん」
無邪気かつ簡潔にこくり。今度は僕がはあっと溜息。
「幸せになるのは難しいなあ……」
「そんなことないよ」
ほんわりと笑って、カウンターの方を向く。
「マスター、窓開けていいですか?」
薬缶が湯気を立てはじめた音と一緒に、どうぞ、という声が聞こえてきた。
彼女は自分の家みたいに、真鍮製らしい古い締め具を外して、窓枠に手をかけて……
「……開かない」
「僕がやるから」
椅子から腰を浮かして、いっぱいに手を伸ばして、彼女の隣の窓を押してみた。
たしかにちょっと立て付けが悪く、不満を言うみたいに蝶番がぎいっと鳴る。
「そーっとね、音を立てちゃダメ」
「……努力はします」
よくわからないけれど、慎重に、少しずつ、古い窓を外側に開いていった。
ひんやりとした風が入ってきた。
それから、空気にお酒を溶かしたような、とろけるような甘い香り。
「……あれ?」
「やっとわかったんだ」
そうしてひょいっと窓の外を指さす。生け垣の奥に、子供の背丈ぐらいのこんもりとした木が植わっている。小さなオレンジ色の花が、あとからまぶしたみたいにそこここに咲いていた。
僕が今まで存在にさえ気づかなかった、正真正銘キンモクセイの木だった。
「それと、あっち」
指をひょいっと下に動かす。
地面の日だまりにクロネコもいた。まだちっちゃい仔猫だ。キンモクセイの香りに包まれて、毛糸で編んだもこもこのクッションみたいに丸まって眠っている。
「ほらね、簡単。気づかなかった?」
いつもの澄まし顔で、でも得意そうに言う。
「うん、気づかなかった」
これには僕も、素直に感服するしかなかった。
「あそこのキンモクセイ、先週咲いてなかったよね。匂いも今日がはじめてだった。だから、今年はじめてのキンモクセイ。あと、クロネコもキンモクセイはじめてでちょっとびっくりしてたけど、今はお気に入り。だから、今年はじめてのクロネコとキンモクセイ」
クロネコの気持ちまで丁寧に説明してくれる。例によって根拠は特になさげだけど、たぶんそれで合ってる気がする。
それはそれとして、重大なことに気づいた。
「もしかしてだけど……今話してたのって、わりと見たまんまの即興?」
「どうかな?」
お待たせしました、と言って、マスターがお代わりを持ってきてくれた。
僕の前にブレンドコーヒー二杯目。彼女の前にはご所望通りのウィンナティー。こんもりとした生クリームの上、シナモンパウダーがたっぷりかかっている。シナモンたっぷりで!なんてオーダーしなくても、最初からこうしてくれるようになって、もう半年は経っている。
愛おしそうにカップを持ち上げ、クリームの山にそっと唇をつける。
「人生に必要なものとか、たくさんありすぎてわからないけど」
シナモンまぶしの生クリームを唇の端にくっつけて、彼女はこっちをまっすぐに見つめる。
「クロネコとキンモクセイだけは絶対必要」
それはきっと、ずっと変わらない宇宙の法則だった。
おわり